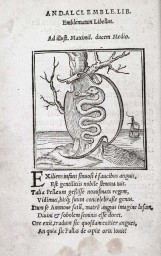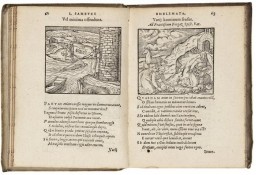個展Emblemataに寄せて
——- 絵は黙せる詩 詩は語る絵 (シモニデス)
現代の人々がエンブレムと聞いて思い浮かべるのは、ブレザーの胸ポケットを飾るワッペンや、制帽の徽章といったアクセサリーであろう。伊藤博明著『綺想 の表象学』(ありな書房)によると、エンブレムとは、「填め込まれたもの」を意味する古ギリシア語 ἔμβλημα (emblema)に由来し、古ラテン語emblemaは、象嵌細工やモザイク作品を意味した。また、食器などの器に取り付ける、着脱可能な装飾部分を指 す語でもあった。すなわち、この語が意味する物体の用途は、古い時代から装飾、アクセサリーだった。ワッペンであれ、ブローチであれ、盾形や円形といった 制限された区画の中に、必要な視覚的情報を構成し、美しく填め込んだ工芸、デザインのことである。
ところが、1531年、アウクスブルクの書肆ハインリヒ・シュタイナーから"Libellum emblematum"(諸エンブムレムの小書)<fig.1>を刊行したアンドレア・アルチャーティは、自らの詩集をemblemata(エンブレマー タ)(=エンブレム集)と称した。その意図は、個人や団体の姿勢やシンボルを表わすための、例えば出版社票のデザインなどに、自らのエピグラムがアイディ アを提供するだろうとの計らいだったらしい。この著書のエピグラムの一々に、丁寧に小さな版画の図版を入れて出版をプロデュースした書肆の狙いは大当たり し、以後、このアルチャーティの書は版を重ねて、欧州中のエンブレムブックの規範となり、後続の出版はバロック期に向かって隆盛を極めていく。当時は大変 もてはやされた文学ジャンルであったため、アントワープに巨大工房を構え、若きルーベンスを指導したオットー・ファン・フェーン(オットー・ウェニウス) なども、幾つかエンブレムブックの傑作を手掛けている。
エンブレムブックにおける「エンブレム」とは、モットー(表題)、図像、エピグラム(銘文)から構成され、一般的な道徳(あるいは宗教的な徳)を説くも ので、図像は言葉によって完全に解き明かされるものだった。今の図解本のようなものであったと言えようか。その一方、王侯貴族の個人的な意図や願望を象徴 的に表現するインプレーサ(仏語でドヴィーズ、英語でデヴァイス)というものが存在したが、それらはモットーと図像から構成され、エンブレムとは区別され るものであった。(だが、図像とテキストが協働して何がしかを象徴するという点では共通しており、このジャンルにも、興味深い仕事が残されている。)
このような一般的な徳や教訓などを説く主流のみならず、ミヒャエル・マイヤーの 『逃走するアタランタ』(1617)のような錬金術の著作もまた、エンブレムブックの形式を採用した。<fig.7>そして、1677年にフランスで出版 された『沈黙の書』<fig.8>に至っては、テキストは黙秘の内に掻き消え、読者に秘術を伝えようと紙面に繰り広げられるのは、不器用な風貌で賢者の石 づくりを励行する一組のカップルをめぐる15枚の図像だけである。
思えば四半世紀の昔、銅版画を始めた頃だったか、白水社のヘルメス叢書にて、この無言のエンブレムを見たときの胸騒ぎが、現在に至る私にとっての長旅の 出航だったかもしれない。その時の奇妙な感覚は、ミュージアムにて万人の胸を震わす一枚の傑作の前に立つときのものとも異なり、熟読するのに労を要する名 著に自室で挑むときの高揚感とも一線を画す。そもそも錬金術の秘法を研究するでもない異国の門外漢にとって、ここに書かれているはずの叡智を読むなど、文 字が書かれていなくとも文盲の読書である。文盲と白状するならば、ラテン語やらオランダ語やら異国の言語で書かれたモットーやエピグラムに伴われた大方の エンブレム図像についても同じことが言える。
しかしながら、エンブレムブックに収録された異国の図像の数々を、文盲ならではの嗅覚でサーヴェイしていると、絵師の創意工夫だったのか意図せざる技 だったのか分からないが、その意味することが理解できなくても、ある特別な体験が生まれることがある。それは、イマジネーションの扉が開き、現代科学風に 言えば異次元宇宙への扉が開くようなもの、と言ったら大袈裟に聞こえるだろうか。邯鄲の中に入るように、図像の中の刷りの余白、2次元宇宙に引き込まれる 一瞬。時には、無名に近い絵師たちが作ったあまりにも素朴な図像もあるというのに、それだけの力を秘めているというのは、いったい何故なのか。美術興行の 手垢に塗れることなく、ただ読者との出会いを期待して、読まれるための舞台である「書物」の内に身をそっと潜ませていたからなのだろうか。つくづく、絵を 描くという行為には、測り知れない秘密がある、と思う。何万年も前に描かれた岩窟の絵や骨片に刻まれた紋様など、美術史が考古学になる刻限まで遡って思い を巡らせてみると、息長く遙か彼方まで越境して、人々の記憶に寄生し続けるのは、マッチ箱の図案に繰り返されるような、ささやかなイコンなのかもしれない などと夢想する。
2次元宇宙にせよ、過去への遡行にせよ、いずれにせよ此処ならぬ彼処への扉を、異国の黴臭いグラフィックに見出すのは、おそらく私個人の異国趣味なのだ ろう。だが、そのようにして異次元のものに結ばれるまま、自分なりの図像を紡ぎだすとき、現代日本を生きる日々の体験が、そのグロテスクな現身を脱いで、 より生々しく迫ってくる。白々としたページの余白は質量を増して黒い天体となり、天地の無慈悲も、人の世の不条理も、小さな慰めの数々も引き込んで益々輝 き、愚かで強靭な生命である私たちを、無情に照らし続けるかのようだ・・・
今回の個展に際し、数多の楽しみをもたらしてくれた図像たちに謝意を表しつつ、勇を鼓して『エンブレマータ』と題打った。そして、絵が仕上がるたびに添 える画題は、描かれたものに唯一言葉の窓を穿つ点で、インプレーサにとってのモットーに見立ててみよう。あとは、ルネッサンスの賢人よろしく『ギリシア詞 華集』を模したエピグラムでも物せればエンブレムとして恰好がつくが、そんな教養も詩才もないので、かつての定型を再現することなど意図できるはずもな い。ただ、エンブレムブックのページのように、絵と言葉が主従関係でなく共振するような場が作れたらと願い、制作中の戯れに書き散らす小文を、会期中、即 興演奏と共に朗読する。
<fig.1>アンドレア・アルチャーティ『諸エンブムレムの小書』(1531)より
<fig.2>ヨハネス・サンブクス 『エンブレム集』初版(1564)
ハプスブルク皇帝ルドルフ2世に仕えた歴史家が収集した167のエンブレム集。各ページに、モットー、図版、エピグラムで構成するエンブレムブックの定型。

<fig.3>オットー・ウェニウス『ホラティウスのエンブレム集』第三版(1612)
図版は大きく扱われており、見開きの左ページにホラティウスの詩を中心としたテキスト。
<fig.4>ヘルマン・フーゴー『敬虔な欲望』英語版(1679)
イエズス会士による、キリスト教エンブレム集のベストセラー
<fig.5>パオロ・ジョーヴィオ『戦いと愛のインプレーサについての対話』リヨン版 (1559)
フランソワ1世のサラマンドラのインプレーサが、対話中に挿入されている。
<fig.6>クロード・パラダン『英雄的ドヴィーズ集』英語版(1591)
このドヴィーズが伴うモットーは「興味深き、自然の模倣者」
<fig.7>ミヒャエル・マイヤー『逃走するアタランタ』(1617)
扉ページに大きくEMBLEMATAと掲げられている。標語とエピグラムを伴う50の図版、さらに、マイアー自身によって作曲された音楽で構成されている。
<fig.8>作者不詳『沈黙の書』(1677)
錬金術の最終段階を表わす最後のエンブレムには、Oculatus abis(目を与えられ、汝は発つ)の言葉がある。